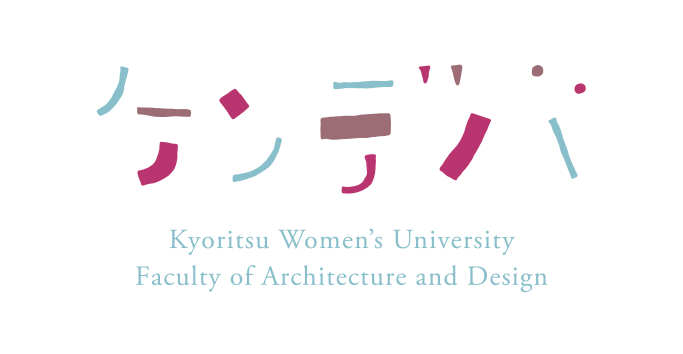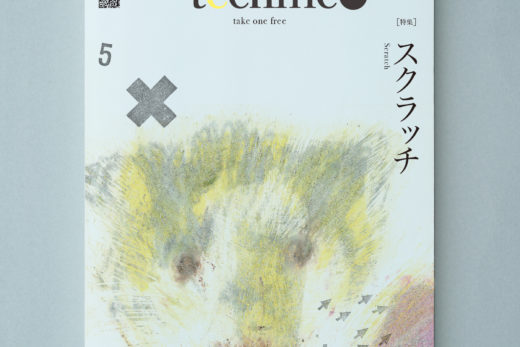共立女子大学建築・デザイン学部連続セミナー2025第1回が、2025年6月7日(土)に開催されました。今回は、本学部客員教授に着任いただいた朝日新聞編集委員の大西若人先生をお招きし、「博覧会・芸術祭と建築デザイン」をテーマにご講演いただきました。
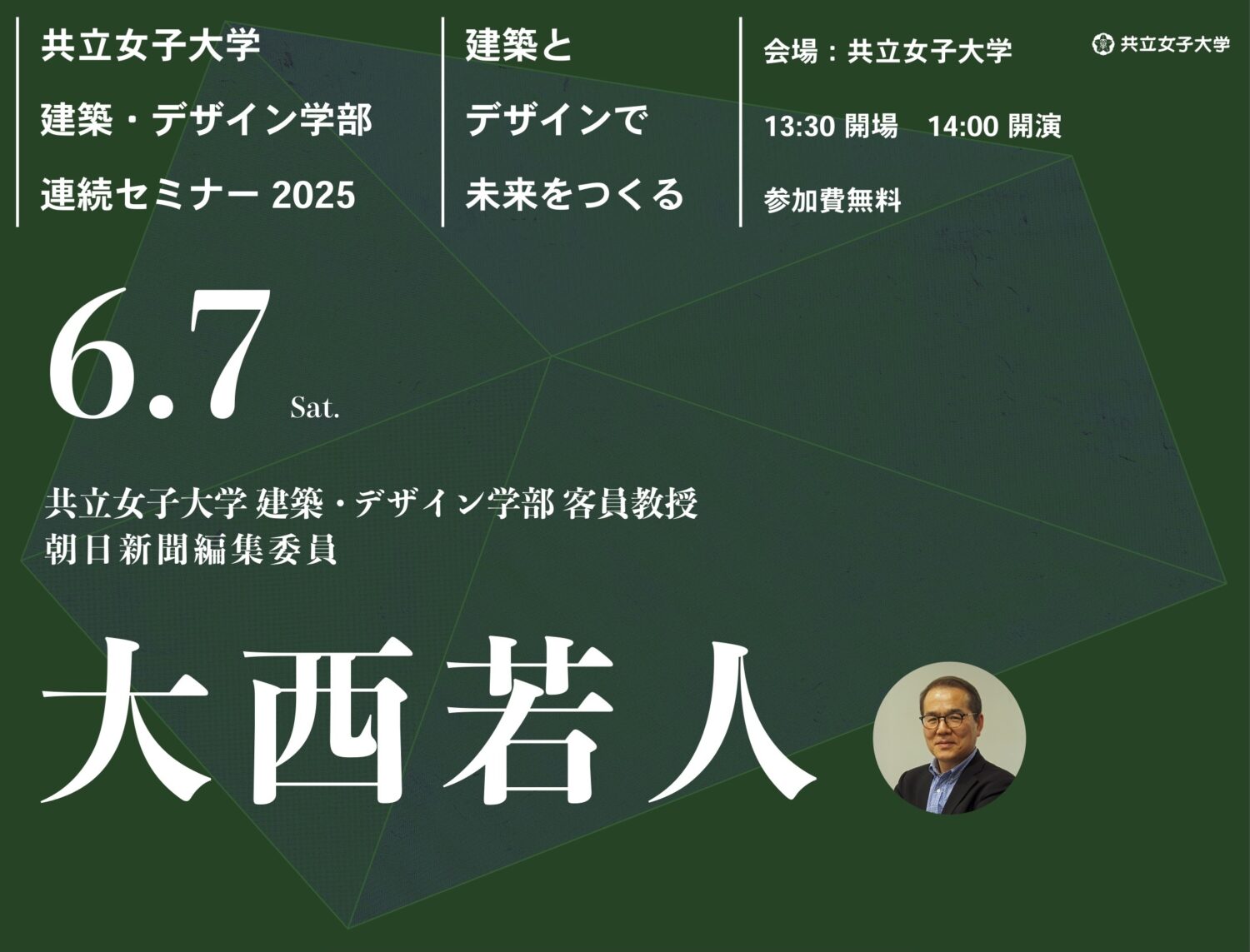
共立女子大学 建築・デザイン学部 連続セミナー2025 第1回
日時:2025年6月7日(土) 14:00開演
会場:共立女子大学 本館
ゲスト:共立女子大学 建築・デザイン学部 客員教授/朝日新聞編集委員
大西若人

大西先生は、アート・デザイン・建築を長年にわたり横断的に取材・論評されており、建築とデザインの融合を掲げる本学部にとって、まさに最適な講師をお迎えする機会となりました。先生が昨年刊行された『ARTとカラダと現代建築』を拝読しましたが、ジャンルを超えた幅広い取材の蓄積に驚かされると同時に、「カラダ=身体性」に早くから着目し、その視点からアートや建築を論評されていることに強く感銘を受けました。VR/ARなどデジタル技術が隆盛する現代において、むしろ物理的な「生の身体」の重要性が高まっているのではないかと感じさせられ、過去の取材記録であっても新鮮さを失わないのはそのためだと考えます。

導入では、今年話題となっている万博を取り上げられ、その歴史の紹介から始まりました。続いて、現在開催中の大阪・関西万博の取材を通じた所感を語ってくださいました。大催事場(EXPOホール)を設計された伊東豊雄氏への取材において、「ほとんどのパビリオンが映像展示だが、今回のテーマである<いのち>を果たして映像だけで感じ取れるのか?」という疑問を呈されたそうです。伊東氏はそのアンチテーゼとして、「力強い命」を建築として示すべく、大地から湧き上がるようなデザインを採用しました。このエピソードは大西先生の語る「身体性」とも響き合い、非常に興味深いお話でした。 続いて芸術祭について、世界で最初の芸術祭であるヴェネチア・ビエンナーレを皮切りに、日本特有の地域型芸術祭についてご紹介いただきました。日本の芸術祭では建築自体が作品として展示されることも多く、建築とアートの境界が良い意味で曖昧になっているのではないか、という指摘は印象的でした。

後半は学生とのトークセッションが行われました。世界の第一線で活躍する方がどのような視点と思想で社会と向き合っているのかを直接伺えるのは、学生にとって貴重な機会です。一方で、学生側が意図する答えを引き出せるかどうかは、ある意味で真剣勝負でもあります。取材における着眼点や心構えについて問われた際、大西先生が「事前の情報に頼らず、第一印象を大事にする」と答えられたのが印象的でした。「情報を先にインプットしてしまうと、主催者や制作者の意図した見方に誘導されてしまう。建築も同じで、写真だけで見るより、30秒でもいいから実際に建築を体感すべきだ」とのお言葉は、本学が学生に最も伝えたいことと重なり、感性はアートや建築と物理的に向き合うことで磨かれるのだと改めて示していただきました。

質疑応答では、私自身も「身体性」というキーワードの現代的意義について質問させていただきました。大西先生は「デジタルやVRに身体性が欠けているという単純な話ではなく、むしろより生々しいものの価値が高まっている。『身体』が重視されるようになった背景には、アイデンティティが一層重要視されるようになったことや、パンデミックを通じて命を深く意識するようになったことがある。建築やアートもその価値観を『身体』から語ることが増えているのではないか」とお答えくださいました。学生には少し難しい話だったかもしれませんが、私は「現場に行って体感しろ!」というメッセージとして伝わったのではないかと思います。

これまでのセミナーでは、建築やデザインの最前線で活動される実務家をお招きすることが多くありましたが、大西先生は「専門を社会に伝える立場」からの視点を提示してくださいました。内部にいると見落としがちなことや、作り手がガラパゴス化しないための外部的視点の重要性を改めて実感させられました。今回のご講演を通じて、アート・デザイン・建築に対峙する際の柔軟で開かれた姿勢を学ばせていただきました。大西先生に心より感謝申し上げます。

文:構造研究室 萩生田 秀之