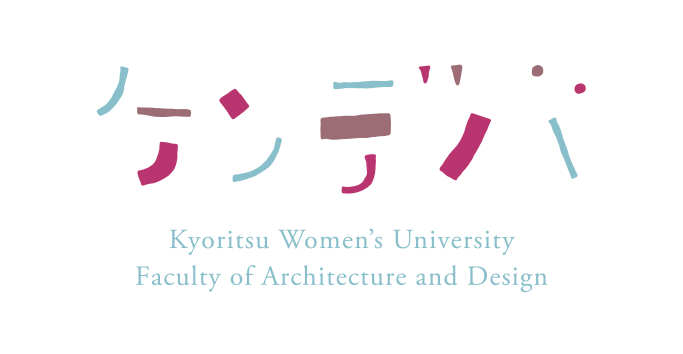友人達のライブパフォーマンスに参加すべく、池尻から恵比寿まで徒歩でフミ散歩。アンダーグラウンド臭のするカオスなライブパフォーマンスは大好物。苦手意識のある表現も理解などしようとせずに、心を解放して自由に体感して欲しい。新しい自分が見つかるかも?

『Law-technology? High-quality!」
佐藤好彦 メガネ 毛利悠子
最先端ではないが完成度の高い、いわゆる「ローテク」で高度に洗練された作品、シンプルで強靭な作品、新たな概念を提示する作品を制作する作家(佐藤好彦、メガネ、毛利悠子ほか)を紹介。情報弱者を生むハイテク偏重の時代において、人間の身体に近いテクノロジーの未来を探ります。
日時:2023年2月2日(木)~2月12日(日)11:00-19:00(最終日は18:00まで)
会場:AL 東京都渋谷区恵比寿南3-7-17
料金:500円
企画:TRAUMARIS 住吉智恵
いわゆる「ローテク」というと、何を思い浮かべるだろうか。たとえばミシンや照明器具、カセットやフィルムの再生機器、自転車や印刷機、古今東西の楽器などの製品がすぐに挙げられるだろう。これらの中には発明されてから数世紀以上にわたるものもある。その多くは主にアナログ・テクノロジーで、基本の構造やデザインをあまり変えずに使用されている。また多くは衣服や灯り、音楽といった、人類の生活に必要不可欠なものを生産するために用いられてきた。
「ローテク」とネット検索すると、一般的に「最先端のデジタル・テクノロジーではないが、技術の完成度が高いテクノロジー」を指すことも多いようだ。「新規事業や新商品を考案する者にとっては、しばしばローテクとハイテクをいかに組み合わせるか、というところが腕の見せどころとなる」といった説もある。
現代美術の分野にも、技術的には「ローテク」でありながら、高度に洗練された作品、シンプルで強靭な作品、あるいは新たな概念や気づきをもたらす作品を制作するアーティストがいる。
佐藤好彦は、千手観音のようなマルチネックのエレクトリックギターや約3mに増幅されたスピーカー内蔵スクーターといった、楽器や音響機材の彫刻作品を約四半世紀にわたり創作し続けている。自らもギターを演奏する佐藤は、現代の量産品特有のプロダクトデザインと自身の音楽体験に基づき、機械的にブーストされた音をめぐる実感を過剰に視覚化する作品を制作してきた。本展では金子マリに「つけま(つ毛)ギター」と命名されたギターの作品や、Charのデビュー45周年のアニバーサリーイヤーに発表されたアルバム『Fret to Fret』(2021)のために制作されたオリジナルギターの作品を展示する。
覆面ポールダンサー・メガネは、研究者の技術協力を得て開発した特殊なポールマシンを操り、ポールダンスの回転によって発電機を回し、微弱電力を発電するパフォーマンスを行う。2011年の原発事故による電力規制下で着想された「自家発電ナイト」では、音楽家やダンサー、美術家、俳優、詩人、画家など多様な分野のアーティストが集い、長時間にわたりメガネが発電する不安定な電力だけを頼りに創意工夫したパフォーマンスを繰り広げてきた。大容量の電力を使ったライティングや音響に依存するライブイベントのありようを問い直し、生身のパフォーマンス表現の底力を照らし出す、瑞々しい取り組みである。本展会期中に約7年ぶりに、佐藤好彦の参加を迎えて開催される予定。
毛利悠子は「箱」にまつわる2つの作品を展示する。ひとつはコロナ禍の2020年「ダークアンデパンダン」展(※)に出展された、USBに格納されたデータによる作品だ。美術館やギャラリーの「ハコ」を脱却した本作は、デュシャンのトランクの如く、軽量で、幾重にも折り畳まれ、謎に包まれた「箱」である。同展では主催者に選ばれた観客だけに鑑賞の機会が提供されたが、今回は佇まいを更新し、会場ALを訪れて「箱」を入手した人に向けて展示される。
もうひとつは、自作のブラックボックス型モニターで、ジガ・ヴェルトフ監督のサイレント映画『これがロシヤだ/カメラを持った男』(Cheloveks Kinoapparatom 1929年ソ連)から毛利の手によりカットアップされた映像を上映する立体作品。当時最先端の特撮技術を駆使し、できたばかりの共産主義国の街を撮影した映像が、ブラウン管テレビを模した手作りの箱に映し出される。
本展では、彼らの展示風景の向こうに、ともすれば情報弱者を弾き出すブラックボックスを生み出す、「ハイテク」偏重の社会を反転して見せようとしている。テクノロジーの肥大化に置き去りにされたかのように見える「ローテク」を見事に昇華させた作家たちの表現を、半ば後退りしながら照射することによって、未来の身体性と親和するテクノロジーの可能性を探るきっかけとなればと思う。
アートプロデューサー/RealTokyoディレクター
住吉智恵